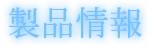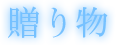Gallery画 廊 |
神凪ノ杜 龍神奇譚

物語

- 木南 瑞希
- 「…………」
- ふと耳に聞こえた雨の音に、
沈んでいた意識が浮かぶ。
ぼんやりと天井を見つめたまま
数度瞬きをすると、すぐ傍で誰かが
こちらに向かって身を乗り出す気配がした。
- 日向
- 「瑞希……! 目が覚めて……」
- ゆっくりと声のした方へ目を向けると、
見知らぬ男の人が心配そうに私を見つめていた。
- 木南 瑞希
- 「……だれ……?」
- 日向
- 「……!」
- 尋ねてからふと気付いた。
……私、何も分からない。
この人の名前だけでなく、
今自分がいるこの場所のことも、
自分の名前すらも……分からない。
思い出そうとしてみるけれど、
霞がかかったように頭がぼんやりとしていて、
何も思い出せない。

- 深く息を吐くと、力が抜けて
少し身体が楽になった気がした。
午前中、大したことはしなかったのに、
とても疲れてしまっていたみたいだ。
部屋の中は穏やかな日の光に包まれていて、
仄かにあたたかい。
開け放たれたままの障子からは
たまにそよ風が吹き、優しく頬を撫でた。
- 木南 瑞希
- 「…………」
- 目を閉じてまどろんでいると、
どこからか微かに子どもたちの
はしゃいだ声が聞こえてくる。
屋敷の近くで遊んでいるのだろうか。
楽しそうに遊ぶ子どもたちの様子が
思い浮かび、思わず笑みをこぼす。
そっと目を開けると
葵くんを挟んだ向こう側で
東雲さんも私と同じように微笑んでいた。

- 木南 瑞希
- 「わ……!
すごい、羽に触ったら色が変わるの?」
- 木南 瑞希
- 「綺麗だね、旭」
- 思わずはしゃいで顔を上げると、
思ったよりも近くに旭の顔があった。
心臓が小さく音を立てる。
- 旭
- 「……記憶があってもなくても、
お嬢様は、お嬢様のままです。
何も変わっていません」
- 旭
- 「ですから、大丈夫です」
- 旭は私を見つめたまま、優しい声で言った。
……最近ここに越してくるまで、私はずっと
辰蔵さんと連絡が取れていなかったと
聞いていた。
それなら、辰蔵さんの式妖である旭とも、
こうして話すのは最近が初めてのはずだ。
それなのに……どうしてだろう。
旭の言葉はまるで、ずっと昔から
私のことを知っていたみたいに聞こえた。
- 木南 瑞希
- 「ありがとう……」
- 記憶をなくしてから、旭はずっと
私を気にかけて助けてくれている。
優しくて、旭と一緒にいるとほっとする。
けれど、同時にどこか掴めないところがある
不思議な人だとも思った。

- 東雲
- 「元気が出たみたいだな」
- 木南 瑞希
- 「え……」
- 東雲
- 「やはり娘さんは、笑った顔が一番だ!」
- そう言って、東雲さんは
いつもの明るい笑顔を浮かべる。
……私が落ち込んでたこと、
気付いてたんだ。
- 木南 瑞希
- 「ありがとうございます……」
- 気恥ずかしいような、嬉しいような、
複雑な気持ちでお礼を言う。
- 木南 瑞希
- 「あの……東雲さんって、
悩みごととかできたりしないんですか?」
- 東雲
- 「む? 悩みごとならたくさんあるぞ!」
- 東雲
- 「どうやったら際限なく
美味いものを食べられるかとか、
昼寝に一番いい場所はどこだろうかとか」
- 東雲
- 「……とまあ、これは
娘さんの言う悩みごととは少し違うか」
- 苦笑しつつ、
東雲さんは考えるように目を閉じた。
- 東雲
- 「そうだな……。
そう聞くということは、娘さんには
何か悩みごとがあるのだな」
- 木南 瑞希
- 「……はい。
悩んでも、答えが出るような
ものではないんですけど……」
- 東雲
- 「そうか…………」
- 東雲さんは呟くように言うと、
そっと目を開ける。
- 東雲
- 「悩んでも仕方がないことに関しては、
あまり考えず、時に任せるのが一番だ」
- 東雲
- 「焦らずとも、大抵のことは
時が解決してくれる」
- 東雲
- 「ただ……一つだけ。
寂しいのや悲しいのは、よくない」
- 東雲
- 「悩んでそういう気持ちになったら、
一人で居ずに、誰かと一緒にいた方がよいな」
- 木南 瑞希
- 「誰かと……」
- 東雲
- 「ああ。娘さんが一緒にいて、
気持ちが楽になる誰かだ」
- そう言うと、東雲さんは
満面の笑みを浮かべる。

- 日向
- 「俺には分かる。
……分かるんだ」
- 日向くんは、もどかしそうに、
懸命に私に言葉を伝えてくる。
- ……どうしてだろう。
- 日向くんは、まるで本当に桃の心が
分かっているかのようで。
- その言葉の一つ一つが胸に染みて、
堪えきれず涙が溢れた。
- とっさに俯くと、日向くんの両手が私の頬を包み、
顔を上げさせられる。
- 日向くんはぎこちなく、けれどとても優しく、
私の涙を拭ってくれる。

- 木南 瑞希
- 「やめて……っ」
- 聞きたいのは、そんな言葉ではない。
- 何の涙か分からないけれど、
瞳から溢れた涙が幾筋も頬を伝って落ちた。
- 旭は苦しそうに顔を歪めて、
目を閉じる。
- 旭
- 「申し訳ありません、お嬢様」
- ……旭が自分を責める理由。
- ずっと知りたいと思っていた。
- でも、こんな話なら、
ずっと知らないままでいたかった……。
- 木南 瑞希
- 「せめて、わけを話して」
- 旭
- 「……許されるような理由は、何もありません」

- 木南 瑞希
- 「…………」
- 今、何が起こっているのか。
- 頭の中が真っ白で、
状況が理解できない。
- 固まったまま、睫毛が触れ合いそうな
距離にある顔を見つめていると、
大きな手のひらが頬に触れた。
- 薄く開いていた唇の間を、
湿った何かが滑り込んできて……
- 口の中に冷たい液体が、
ゆっくりと流れ込んでくる。
- 木南 瑞希
- 「ん……っ」
- 反射的にそれを飲み込んで、
ようやく我に返った。
- ——水を、口移しされてる。
- 気付いた瞬間、火がついたように
身体が熱くなった。
- 木南 瑞希
- 「や……」
- とっさに顔をそらして、
日向くんの身体を押し返そうとする。
- けれど、朝から何も口にしていなかったせいか、
うまく腕に力が入らない。
- 日向くんは私の抵抗を簡単に抑え込むと、
さっきよりももっと強く私を引き寄せてきた。
- 押し付けるように唇を合わせて、
私の口を開かせる。
- 熱い舌とは対照的に、
口の中に広がっていく水は冷たくて、
なんだか眩暈がした。
- 木南 瑞希
- 「ん……っ……」
- 部屋の中は静まり返っていて、
互いの息遣いだけが、やけに響いて聞こえる。
- それが余計に羞恥を煽って、
心臓の鼓動が激しくなった。

- 木南 瑞希
- 「あ、あの、東雲さん……?」
- 東雲
- 「……何か誓うときは、
こうするのが最近の流行りなのではなかったか?」
- 木南 瑞希
- 「そ、そんなこと、誰に聞いたんですか」
- 東雲
- 「テレビで見たのだ」
- 恋愛ドラマでも見たのだろうか。
- 頭に乗せられていた東雲さんの手が、
そっと私の髪を撫でる。
- その手つきがあまりにも優しくて……
まるで恋人同士にでもなったような錯覚を
起こしそうになる。
- 木南 瑞希
- 「ふ、普通はこんなことしません」
- 東雲
- 「ははっ! そうか、それはすまぬな」
- 言いながらも、東雲さんは
なかなか離れようとしない。
- どうしたんだろう……。
- 困惑して顔を上げようとすると、
止めるように頭を押さえられた。
- 東雲
- 「……ありがとう、娘さん」