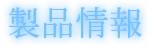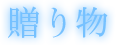Gallery画 廊 |
描き下ろし

物語

- もう七年も前の話なのに、いまだにあの日のことを夢に見ることがある。
- それは自分の心の弱さを表しているようで、そのたびに、そんな自分に嫌気が差した。
- 「兄ちゃん、おきてる?」
- ある日の晩、部屋で勉強をしていると、弟の葵が障子を開けて顔を覗かせた。
- 「何だ?」
- 「こわいゆめみた」
- よく見ると、腕に枕を抱えている。
- 「もう二年生だろ。それくらいで一人で寝られなくなってどうすんだよ」
- 「……ごめんなさい」
- 謝りつつも、葵は部屋に戻ろうとする気配はない。
- 「……寝るまで部屋に居てやるから、自分の部屋で寝ろ」
- ため息を吐いて立ち上がる。
- 「うん」
- 葵はほっとした様子で頷いた。二人で部屋を出ると、葵の部屋に入る。
- 「……荷物、増えたな」
- 部屋の中を見渡して、思わず呟いた。この屋敷へ来たばかりの頃は必要最低限のものしかなかったが、今は時間割が壁に貼ってあったり、おもちゃが並んでいたり、生活感のある部屋になっている。
- 「兄ちゃん……?」
- 三年も住んでいるのだから、当たり前といえば当たり前か。
- 「何でもない。ほら、さっさと横になれ」
- 葵を促して、布団に寝かせる。電気を消して枕元に座ると、月明かりを頼りに持ってきた単語帳を捲った。
- 明日は中間テストがあって、さっきまではその勉強をしていた。けれど、まだ明日の朝飯の下準備をしていないし、葵が寝るまで待った後それを終えたら、もう寝ないとまずい時間になっているだろう。少し目は疲れるが、今のうちに勉強するしかない。
- 「兄ちゃん、それべんきょう?」
- 「ああ」
- 「……おれ、じゃました?」
- 単語帳を捲っていた手を止める。葵を見ると、不安そうに俺を見上げていた。
- 「邪魔なんて思ってねえよ。馬鹿なこと考えてないで寝ろ」
- 「……うん」
- 少し乱暴に頭を撫でてやると、ほっとした様子で笑って、それから目を閉じる。
- がきのくせに、気遣いやがって。一瞬そう考えて……違うと思った。
- こうして他人の家で預かってもらって、少しも気を遣うなという方が無理な話なのかもしれない。こいつは、気を遣わざるを得ない状況に置かれているだけなんだ。
- 微かに寝息をたてる、あどけない寝顔を見ていると、もどかしい気持ちになる。
- こいつはまだまだ子どもで、本当は親にだって甘えたい年頃で。だけど、俺がいくら努力したところで、本当に親の代わりになれるわけはない。
- もどかしくて……やりきれない。
- どこにいんだよ……」
- 幼い頃に見たきりの、もうおぼろげな顔を思い出して、思わず小さく呟いた。

- 「なあ宋太、進路希望調査の紙ってもう出した?」
- 学校の昼休憩、一緒に昼ごはんを食べていた男子の一人が、ふと思い出したように聞いてきた。
- 「……ううん。まだだよ」
- 「そっかー、よかった宋太もまだで!」
- 俺が答えると、心底安堵した様子で胸を撫で下ろす。
- 「馬鹿。お前、宋太と自分が同じだと思うなよな」
- 「宋太は頭いいから進路選び放題だけど、お前は死ぬ気で勉強しなきゃどこにも受かんねえよ」
- 「う、うるせえな! それはお前らも一緒だろ!」
- いつものように言い合いを始めたみんなを、苦笑しつつ眺める。
- 高校二年生になって、最近は進路の話をすることが増えてきた。みんなは将来のことで思い悩んで、模擬試験の結果に一喜一憂したりしていて……けれどそんな中、自分だけはどこか冷めた気持ちでいた。
- 高校を卒業したら、きっと大学に進んで、大学を卒業したら、今度は社会人になって。そんな未来は容易に想像がついた。
- 自分の将来に、不安はない。けれど、その代わりそこには少しの期待もなかった。
- みんながタイムカプセルの中にきらきらと輝く夢を詰めている中、自分一人だけ空っぽのタイムカプセルを埋めているような、そんな虚しさが胸にあった。
- 「あれ、宋太のスマホ鳴ってねえ?」
- 「あ、本当だ」
- スマートフォンの画面を見ると、伯父からの電話だった。
- 「……ごめん。ちょっと外すね」
- 「おー、早く戻ってこいよ」
- みんなに手を振って足早に教室を出ると、人気のない廊下まで歩いていき、電話に出た。
- 「……もしもし」
- 「宋太か? 悪い、今学校だよな。時間大丈夫か?」
- 「大丈夫だよ。休憩時間だから」
- 「そうか……。なら少しだけ、母さんと話してやってくれないか?」
- 「……うん」
- 俺が答えると、スマートフォン越しに伯父さんが母さんを呼ぶ声が聞こえてくる。
- 「——もしもし?」
- しばらくして聞こえた、高くか細い声に、小さく深呼吸してから口を開いた。
- 「もしもし、母さん。どうしたの?」
- 「理由なんてないわ。ただあなたの声が聞きたくなっただけよ」
- 「……そっか」
- 相槌を打ちながら、制服の襟元をぎゅっと握り締めた。
- ……母さんの声を聞いていると、自分の中の何かが擦り切れていくようで、息が詰まりそうになる。
- けれど皮肉にも、このときだけが唯一、自分が確かに自分であると感じられるときでもあった。
- 「週末は帰って来るのよね? 楽しみだわ」
- 母さんの言葉に、微笑んで目を閉じる。
- 「うん……。『俺』も、楽しみだよ」

- 夕暮れ時、いつものようによろず妖屋の依頼を終えて屋敷へ帰っていると、道の脇を流れる小川から水が跳ねるような音が聞こえてきた。
- 何かと目を向けてみると、小さな白い狐のような生き物が川で溺れていた。
- 「……妖か」
- そう判断すると、止めていた足を踏み出す。溺れている妖に向かってではなく、屋敷のある方に向かって。
- よろず妖屋の仕事で、依頼を解決するために必要であれば妖を助けることはあるが、それは別に善意でやっているわけではない。無闇に首を突っ込んでも面倒ごとに巻き込まれるだけだ。
- 本来妖は人には見えないもので、関わることのないものなのだから、放っておけばいい。
- 「だれかっ! たすけてっ!」
- 「…………」
- 「たすけてーー!」
- 「………………」
- 歩く速度と溺れる妖の流れる速度が同じくらいなせいで、常に脇から悲鳴が聞こえてくる。
- 「だれかー!」
- 「……分かったから、静かにしろ」
- これは妖を助けるためではなく、うるさい悲鳴を止めるためにやることだ。
- ため息を吐いて、俺は妖を川から引っ張り上げるべく土手を下りた。
- 「たすけてくださって、ありがとうございました」
- 助けた狐の妖はまだ子どもなのか、少し舌足らずな口調で言って頭を下げた。
- 「ぜひぼくのお家にあそびにきてください。おもてなしします」
- 「ああっ、おまちください!」
- 歩き出そうとすると、着物をくわえて引き止められる。
- 「おい、離せ」
- 「お父さんとお母さんにも、いのちのおんじんさまをしょうかいしたいのです」
- 妖の口から着物を外そうと布を引っ張るが、妖は離そうとしない。
- これ以上強く引けば、着物が破れそうだ。辰蔵さんから貰った着物を傷付けたくはない。
- 「……分かった。分かったから、離せ」
- 妖が俺を連れていったのは、近くの町の新興住宅地だった。
- 「お父さん、お母さん。みてください。ぼくのおんじんさんです」
- 妖は嬉しそうに跳ねながら、新築の家の脇にある茂みへ向かう。
- 茂みには、俺を連れてきた妖によく似た狐の妖が二匹寝そべっていた。
- 「ねえ、まだねてるの? せっかくおきゃくさんがきてくれたのに」
- 妖が鼻先で突いても、二匹の妖が起きる気配はない。
- 俺は茂みの前にしゃがみ込み、二匹の妖の身体に触れてみた。冷たく、硬い感触が手の平に伝わる。
- よく見ると、二匹の妖の身体には打撲の跡のようなものがあり、茂みの傍には壊れた巣の残骸のようなものがあった。
- 「おんじんさん、ごめんなさい。ふたりがおきたら、またお家にきてくれますか?」
- 妖が申し訳なさそうに俺を見上げる。俺はその頭にそっと手を乗せた。
- 「……ああ。分かった」


- 「お、掛かってるな」
- 日の沈みかけた薄暗い山の中、高耶が道の先に立つ妖を見て言った。
鹿によく似た妖——まだ子どもだ。
俺が張った結界の罠にかかり、身動きがとれなくなっている。
妖は俺と高耶に気付くと、怯んだように顔を引きつらせた。
- 「お前ら……よろず妖屋の式妖か」
- 「ご名答。俺たちも有名になったもんだな」
- 高耶は楽しそうに笑いながら、懐から短刀を取り出す。
- 「さて、さっさとこいつ始末して帰るか」
- 高耶の言葉に、妖が身体を強張らせる。
- 「……殺す必要はないだろう。怯えているし、脅すくらいで十分だ」
- 「何言ってんだ、旭。依頼人の家の近くに、もう二度とこの妖を近付けるなってのが主の命だろ。なら殺すのが一番確実じゃねえか」
- ……式妖としては、高耶の考え方のほうが正しいのだろう。
再びこの妖が依頼人の家に近付くことがあれば、俺たちは罰せられるが、殺しても咎められることはない。
むしろ辰蔵様は妖に対していい感情を持っていないから、殺した方が喜ばれるのかもしれない。……だが。
高耶が妖に向かって短刀を振り下ろす。俺は反射的に自分の短刀でそれを受け止めた。
金属のぶつかり合う、甲高い音が響く。
- 「……何の真似だ」
- 高耶の顔から笑みが引いた。
黙っていると、高耶は俺に近寄り胸倉を掴んでくる。
- 「いいか。式妖は主の命であれば、どんな汚いことでもやる。逆らえば命が危ういからな。……でもそれは、自分の行為を正当化する理由にはならねえ」
- 「……分かっている」
- 「分かってねえから言ってんだよ。この偽善者が」
- 苛立ちを露わに、高耶が睨みつけてくる。
- 「お前はずっと、自分の命と他人を天秤にかけて、自分を選んできたんだ。……あのときだって、そうだっただろ」
- 高耶が言った瞬間、脳裏に記憶がよみがえる。全身から血の気が引いて、暑くもないのに汗が噴き出してきた。
- 「お前すぐに主んとこ報告に行ったから、見てないんだよな。あの後——」
- 「やめろ」
- 眩暈がして、力なく高耶の身体を押し返す。
- 「……頼む。もう、分かった」
- 高耶は小さく笑って、ようやく俺から手を離した。
- 「後は任せたからな」
- 「……俺を殺すのか」
- 高耶が去った後、妖に向き直ると怯えた顔でそう聞かれた。
黙ったまま近付くと、妖を捕らえていた結界を解く。
- 「もうあの家には近付くな。近付けば、今度こそ命はない」
- 妖は戸惑った顔をしていたが、すぐに踵を返して逃げていった。
……高耶のように式妖として割り切って働くこともできず、かと言って、たとえ殺されても構わないと自分の信念を貫くこともできない。
中途半端で、愚かで……吐き気がする。
風が吹いて、腕に付けた鈴が鳴った。それをそっと手で押さえ、歩き出す。
自己嫌悪と罪悪感で押し潰されそうな日々。……だがそれも、きっともうじき終わるだろう。
『その時』が来たら、今度こそ俺は正しい選択をする。
たとえ、何を失うことになっても。

- 「お母さん、お皿」
- 「ありがとう。瑞希、日向」
- コンロの前に立っていた都に皿を手渡し、朝ごはんを載せてもらうのを待つ
- 「二人とも、目玉焼きは醤油と塩どっちがいい?」
- 都が聞くと、瑞希は少し考えて顔を上げる。
- 「わたしはしょうゆがいい」
- 「……じゃあおれも、しょうゆにする」
- 「日向、また瑞希の真似っこしてる」
- 「おそろいうれしい」
- 瑞希は満面の笑顔を浮かべていた。瑞希の笑顔を見ると、ほっとして、幸せな気持ちになる。
- 「うん。おれも」
- 「二人とも仲良しでいいなあ。お母さんも仲間に入れてほしいから、醤油にしちゃおっと」
- お皿に目玉焼きを載せながら、おどけたように都が言う。
- 「——はい、できた。二人ともテーブルに運んで」
- 「はあい」
- 都から皿を受け取り、瑞希が台所を出ていく。
- 「いこう、日向。はやく食べないと、小学校ちこくしちゃう」
- ……でた。学校。
思わず顔をしかめる。学校は、俺が今一番嫌いなものだ。
- 「瑞希、学校すきなのか?」
- 瑞希の後を追いかけながら尋ねる。
- 「うーん……どうかな」
- 「じゃあ家は?」」
- 「お家はすきだよ」
- 「ならずっと家にいればいいのに」
- 俺は学校には行けない。行ったとしても、普通の人間に俺は見えないから、瑞希も俺を見えないふりしないといけなくて、退屈だ。
家にいたら、一緒に遊んだりしゃべったりしてられるのに。
- 「だめだよ。学校はちゃんといかないといけないもん」
- 「……あっそ」
- つまんねえの。
不貞腐れてそっぽを向くと、窓の向こうに瑞希と同じようなランドセルを背負った人間が数人見えた。悔しいような、羨ましいような気持ちでその後ろ姿を見つめる。
俺が人間だったら、ずっと一緒にいられたのにな……。
- ふと目を開けると、そこは南条邸の縁側だった。
草抜きの休憩をしていて、いつの間にか寝てしまっていたらしい。
……何だか、懐かしい夢を見ていた気がする。
- 「あ……日向さん」
- 背後からかけられた声にどきりと心臓が鳴った。身体を起こして振り返ると、瑞希が一人で立っている。
- 「えっと、草抜きしてたんですか?」
- 瑞希はまるで知らない人と話すみたいに、他人行儀な態度で俺に聞く。
それが耐えられなくて、俺は顔を背けて立ち上がった。
- 「ああ。……それじゃあ」
- こんな、仕返しみたいに素っ気ない態度をとったって、意味はない。今の瑞希は何も覚えていないのだから。
分かっているのに、子どもが駄々を捏ねるみたいに、身体が言うことを聞いてくれない。
- ……多くを望んではいなかった。人間である瑞希と、ずっと一緒にはいられないことも、ちゃんと理解していた。
でも、理解していたからこそ……せめて思い出だけは、心の中に置いていてほしかった。
傍にいられなくなっても、時々思い出して懐かしんでくれたら、それだけでよかったのに。
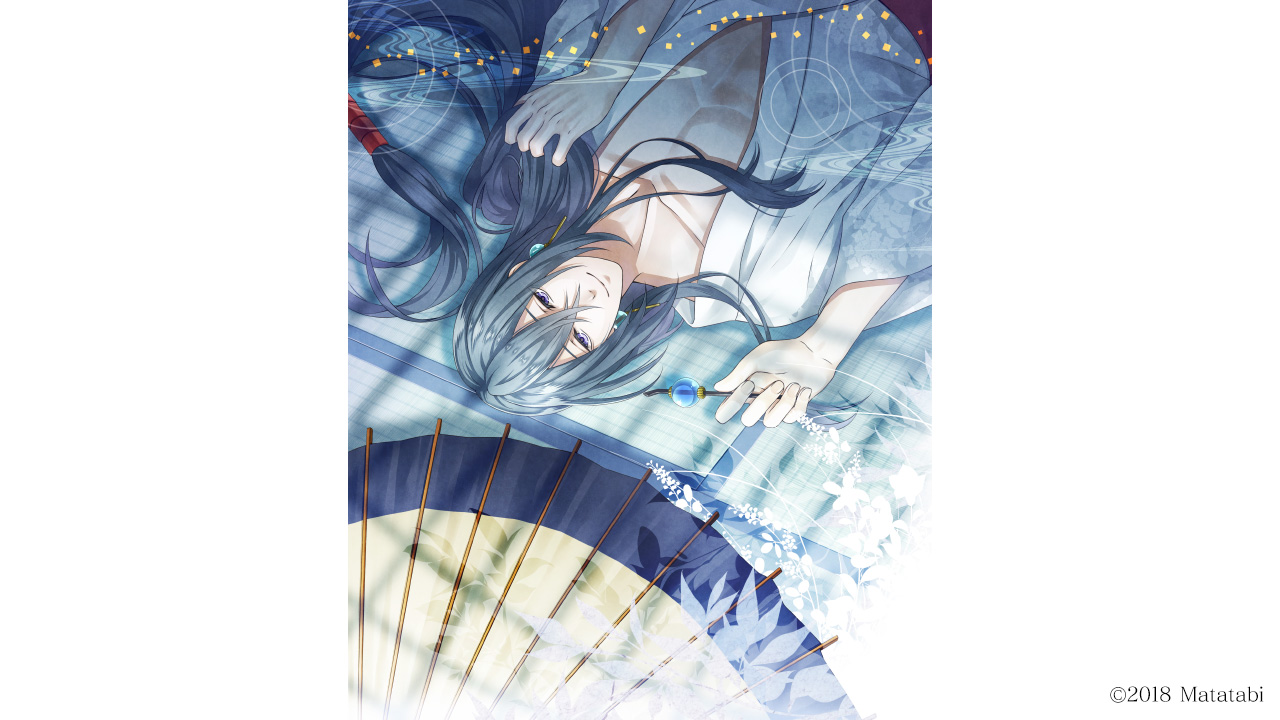
- 全てのものにはじまりがあるように、必ず終わりがある。
富や名誉を得て栄えた者にも、家の軒先に巣を作る小鳥にも、等しく最後のときは訪れる。
例外は何一つなく、この世界さえもいつかはきっと終わりを迎えるだろう。
それは決して覆すことのできない、この世の理だ。
- 朝、村の道を散歩していると、川の向こう岸を歩く白い子狐の妖を見つけた。
腰に帯のようなものを巻いていて、そこに花を数本差している。
- 「やあ、どこへ行くのだ?」
- 声をかけてみるが、聞こえなかったのか子狐は俯いたまま立ち止まることなく歩いていく。
- 「おーい、ちょっと待ってくれ!」
- 橋を渡って子狐を追いかけると、ようやく振り向いてくれた。
- 「ぼくになにか用ですか?」
- 「いや、用というほどのことは何もないが……。どこへ行くのか気になってな」
- 「……たのしいところじゃないですけど、ついてきたかったらどうぞ」
- そう言うと、子狐はさっさと歩き出してしまう。尻尾は垂れていて、その背中はどこか元気がなく見える。
特に行きたい場所があって歩いていたわけでもなし。とりあえず付いていってみるか。
- 「うむ。それではお言葉に甘えるとしよう!」
- 子狐の隣を歩きながら、顔を覗き込む。
- 「僕の名は東雲という。君は何というのだ?」
- 「……綿毛です」
- 「ふむ、綿毛か。確かに尻尾が綿毛そっくりだな!」
- 「わっ! ちょっと、かってにしっぽさわらないでくださいよ」
- 「おお、これはすまぬすまぬ!」
- 笑いながら謝ると、子狐改め綿毛は大きなため息を吐いた。
呆れている様子だが、さっきまでの暗い表情よりはずっといい。
歩きながらそうして何度も話しかけていると、綿毛はたまに笑ってくれるようになった。
- 「……ここです」
- 綿毛は山の中の大きな木の下で、足を止めた。
木の下の土は少し盛り上がっていて、周りにはたくさんの花が置かれている。
- 「ぼくのお父さんとお母さんのお墓なんです」
- 「そうか……」
- 腰に差していた花を取って、綿毛がお墓の前に置く。
- 「お父さんとお母さん、どうしてしんじゃったんでしょう」
- ぽつりと呟くように、綿毛が言った。
その隣にしゃがみ込み、綿毛と同じようにお墓を見つめる。
- 「もし僕が何か理由を言ったとして、綿毛はそれを受け入れられるだろうか」
- 「……それは……」
- 「命以上に大切なものなど、そうありはしないと、僕は思うのだ」
- うなだれてしまった綿毛の頭を、そっと撫でる。
- 「だがな、残された者が意味のあることにすることはできる」
- 「どうするんですか?」
- 「綿毛が父親と母親のことを忘れず、生きていけばよい」
- 死というもの自体には、何の意味もない。死は他者と繋がることで、初めて意味を生むのだと思う。
枯れて落ちた葉や枝が、芽吹いた草木の肥やしとなるように、綿毛が忘れず覚えていれば、両親の死はいつか彼の心の糧となるだろう。
- 「……それだけですか?」
- 綿毛は釈然としないような顔をしている。苦笑して、その頭をもう一度撫でた。
- 「今は分からずともよい。……いつかきっと、分かるときが来る」

- 全てのものに終わりがあるように、必ずはじまりがある。
- 終わりとはじまりは表裏一体で、誰かにとっての終わりは、他の誰かにとってのはじまりだったりする。
- それはひどく残酷で理不尽な、この世の理だ。
- 俺はあの日からずっと、この世の全てのはじまりを憎んでいる。
- 「……今月も見つからなかったか」
- 俺と旭の報告を聞いて、主が呟くように言う。
- 「まあでも俺が今回見つけた手掛かりは、なかなかのもんじゃないっすか?」
- 主は俺を一瞥すると、小さく息を吐いて旭に目を向けた。
- 「そうだな。……今日は旭だけ残れ」
- 「さすが主、慈悲深いことで」
- 恭しく頭を下げてみせる。
- 主は眉をひそめてこちらを見たが、俺は構わず旭に向き直った。
- 「一緒に『罰』受けてやれなくて悪いな。頑張れよ」
- 笑いながら旭の肩を叩く。
- 旭は無表情のまま、俺を見ようともしなかった。
- 旭は無表情のまま、俺を見ようともしなかった。
- ……相変わらず、つまんねえ奴。
- ふんと鼻を鳴らすと、踵を返して主の部屋を出る。
- 『罰』とは俺たち式妖が命じられた仕事に失敗したとき、主が術を使って俺たちを痛めつけることを指す。
- 式妖は契約を交わした瞬間から、主に命を握られている。
- 主から下される命令自体に強制力はないが、その気になれば主はいつでも式妖の命を奪うことができるのだ。
- 俺たちに逆らうという選択肢は、あってないようなものだった。
- 俺が主の部屋を出てから一時間ほどが経った頃、自室で休んでいると、廊下から足音が聞こえてきた。
- 旭だろうと予想して、寝転んだまま障子を開ける。
- 「高耶……」
- 「お疲れさん。……今回は相当きつかったみたいだな。今にも死にそうな面してんぞ」
- 真っ青な顔をした旭を見上げて笑う。
- 「……話はそれだけか」
- ふいと顔をそらすと、旭は再び歩き出そうとする。
- 「待てよ。……お前、本当にまだ見つけられてないのか?」
- 「……どういう意味だ」
- 旭がゆっくりとこちらを振り向いた。その顔を注意深く見つめたまま言葉を続ける。
- 「いや……あれからもう十年以上経つのに、お前が手掛かり一つ見つけられないなんて、妙だと思ってな」
- 「俺が辰蔵様の命を破っていると言いたいのか? それができないのは、お前も百も承知だろう」
- 旭の表情には、少しの動揺も見られない。
- 「……それより、妙なのはお前の方だろう。高耶」
- 「俺のどこが妙なんだ? 今回は手掛かりまで見つけてきたってのに」
- 「それが妙なんだ。いつも俺に任せてばかりいるくせに、どうしてこの仕事には真面目に取り組む」
- 「人聞き悪いな。俺はいつだって真面目だろ」
- にこりと笑って答えると、旭はため息をこぼして、今度こそ俺に背を向けた。
- 「……お大事に」
- 「どうするんですか?」
- 遠ざかっていく背中に声をかけて、障子を閉める。
- 仰向けに転がって目を閉じると、屋根を叩く雨の音が聞こえてきた。
- ……ああ、またこの季節がやってきた。
- まとわりつくような湿った空気。生ぬるい雨。
- 終わりとはじまりの、呪われた季節が。

- 「は? 二人部屋が四つ?」
- 受付から戻ってきた旭の言葉に、思わず眉を寄せる。
- 今日はよろず妖屋の仕事で遠くの町まで来ていた。依頼内容からして仕事が長引くのは予想できていたので、先にホテルを予約しておいたのだが、予約した部屋のタイプが違う。
- 「木南がいるから、二人部屋を三つと一人部屋を二つで予約したはずなんだけど」
- 「仁科様の予約はその通りなのですが、手違いがあったようで。他に空室もないそうです」
- 「困りましたね。辺鄙なところだから、近くに別のホテルもなさそうですし……」
- 話を聞いていた宋太が、スマートフォンの地図アプリを起動させて調べ始める。
- 「うーん、やっぱり徒歩圏内に他にホテルはないし、ネットカフェなんかもないみたいです」
- 「……でしたら俺は外で寝ますので、みなさま
はお部屋で——」
- 「だっ、だめだよ! 野宿なんて!」
- 「宋太の言う通りだ。さすがにそれはねえ」
- 真顔でとんでもないことを言い出した旭を、宋太と俺で止めていると、手洗いに行っていた東雲と市丸さんが戻ってきた。
- 「む? どうかしたのか?」
- 「そうだ、野宿ならこいつにさせた方がいいだろ」
- 「……何の話だ?」
- 訝しげな顔をする市丸さんに、事情を話して聞かせる。
- 「なるほどな……。そういう事情なら仕方がない。こいつは野宿でいいだろう」
- 「そんな、ひどいではないか! 今日は僕もよく働いただろう?」
- 「お前は買い食いしていただけだろう。ついてきたのも、屋敷に一人になるのが嫌だとかいう理由だし、お前にホテル代を使うのは馬鹿らしい」
- 市丸さんがじっとりと東雲を睨みながら言う。
- 東雲は肩を落として口を開いた。
- 「仕方がない、それなら今夜はホテルの前にあった小さな小屋に泊まるとするか……」
- 「小屋? んなもんあったか?」
- 首を傾げると、隣ではっとしたように宋太が息をのんだ。
- 「まさか……あの、緑の屋根のこれくらいの小屋ですか?」
- 宋太が手で大きさを表しながら聞く。その言葉に東雲はぱっと笑顔になった。
- 「そうだ! あれなら雨風はしのげるだろう? 僕は今夜あそこに泊まるぞ」
- 「馬鹿。あれは犬小屋だっつうの」
- 葵と木南とコンビニへ行っていたはずの日向が、いつの間にか戻ってきていて、東雲の背後から呆れたように言った。
- 東雲はきょとんとした顔で目を瞬かせる。
- 「む? そうなのか?」
- 「……駄目だな。こいつを一人にしたら通報される」
- 「そうですね……」
- 市丸さんの言葉に深く頷く。
- どうしたものかと考えていると、事情を聞き終えた日向が口を開いた。
- 「それなら俺は、あいつと同じ部屋でいい」
- 「それは……あまりよくないのではありませんか?」
- 「なんでだよ、旭。俺と一緒ならあいつも安全だろ」
- 「いや、むしろ危険っつうか……。俺も反対だな」
- 日向はずっと木南と暮らしてきたからあまり気にしていないのかもしれないが、木南に対する日向の気持ちはなんとなく分かっているし、同室にするのはなんとなく落ち着かない。
- 「なら仁科が同室になるか?」
- 面倒臭そうに市丸さんが聞いた。
- 俺があいつと同じ部屋……。
- 「それもあまりよくないかと……」
- 「俺も絶対反対だ。こっそりあいつの好物作って、点数稼ぐ姑息な奴だし」
- 「うむ、直はなんというか……むっつりな気がするしな」
- 「……おい。なんでここまで言われなきゃなんねえんだ」
- 俺は何も言ってねえのに、とんだとばっちりだ。
- 「そ、そうだ! それなら市丸さんはどうですか?」
- ギスギスし始めた空気に、慌てたように宋太が言う。
- 「市丸さんか……」
- 木南と市丸さんが、二人で部屋にいる様子を想像してみる。
- ……なんというか。
- 「空気悪くなりそうじゃねえか」
- 「娘さんの気が休まらなさそうだな……」
- 日向と東雲が腕を組んで難しい顔をする。市丸さんに悪いので口にはしないが、俺も同意だ。
- 「それなら宋太はどうだ? 宋太はよく気が付くし、娘さんもきっとゆっくり休めるだろう」
- 「ええっ!? 俺ですか」
- 動揺したように宋太が顔を赤くする。
- 「こいつも絶対駄目だ。好感度がめちゃくちゃ上がる予感しかしねえ」
- 「同じ年頃の男女が同室というのは、やはりどうかと……」
- ……こいつらは誰でも反対するんじゃねえのか。
- 頑なに首を縦に振らない日向と旭を横目に、ため息を吐く。
- 「じゃあどうすんだよ」
- 「……兄ちゃん」
- 服の裾を引っ張られ、振り返ると葵と木南が立っていた。
- 「お前らどこ行ってたんだ?」
- 「日向兄ちゃんと姉ちゃんと三人でコンビニいったあと、トイレいってた」
- 「何かあったんですか?」
- 木南に尋ねられ、簡潔に今の状況を説明する。
- 「それなら、おれ姉ちゃんといっしょにねる」
- 「……葵が?」
- 「そうだね、一緒に寝よっか」
- 葵の言葉に木南も笑顔で頷く。
- 「おれ、トランプもってきたから、へやでやろう」
- 「いいね、楽しみ」
- 「…………」
- 盛り上がる二人に背を向けて振り向く。日向や宋太がなんともいえない顔をしていた。
- ……なんで葵のこと、思いつかなかったんだろう。
- くだらないことに時間を使ってしまった。
- 深く息を吐くと、俺たちはそれぞれ部屋へと向かった。


- 「——みて、ライオンいる」
- 通路の先にある大きな檻に、葵くんが目を輝かせて駆け寄る。そのあとを、私と仁科先輩、宋太くん、市丸さんは歩いて追いかけた。
- 「走るな。転ぶぞ」
- 葵くんの隣に並んで、仁科先輩が頭を小突く。けれど葵くんは既にライオンに夢中で、聞こえていない様子だ。
- 「すごい……つよそう」
- 「怖くない?」
- 私も葵くんの隣に立って、尋ねてみる。
- 「うん。かっこいい。おれ、ライオンすき」
- 「じゃあ観察する動物、ライオンにする?」
- 宋太くんの言葉に葵くんが頷いて、リュックからスケッチブックを取り出す。
今日はみんなで動物園に来ていた。というのも、スーパーの抽選会で仁科先輩が動物園のチケットを五枚当てたからだ。
葵くんはこの機会に夏休みの自由研究をするつもりで、動物園の動物を観察することにしている。
- 「それにしても、晴れてよかったよね。最近雨が続いてたから、今日もどうかなって思ってたんだけど」
- 宋太くんが言って、空を見上げた。頭上には雲一つない青空が広がっている。
- 「そうだね……」
- 日向と東雲さんも、来れたらよかったのにな。
- チケットが五枚しかなかったので、葵くんとチケットを当てた仁科先輩以外はじゃんけんをして、動物園に行くメンバーを決めた。
市丸さんは辞退しようとしていたのだけれど、東雲さんに無理やり参加させられて、結局じゃんけんの結果、東雲さんは行けなくなり、市丸さんが動物園に来ることになった。
- 「そうだ。葵くん、ライオンって犬と猫、どっちの仲間だと思う?」
- ふと思いついたように、宋太くんが尋ねる。
- 「……犬。おっきいし」
- 葵くんは少し考えて、そう答えた。
- 「外れ。猫だ」
- 仁科先輩が言うと、葵くんは目を丸くする。
- 「うそ」
- 「本当だよ。ですよね、市丸さん」
- 「ああ」
- ライオンを見ながら、市丸さんが答える。……行くときは面倒そうにしていたけれど、なんだかんだ市丸さんが一番真剣に動物を見ている気がする。
葵くんは驚いたように「そうなんだ……」と呟いて、再びライオンを見た。
- 「……ライオン、うごかない。ずっとねてる」
- 「夜行性だからな。体力を浪費しないためにも、日中はほとんど寝て過ごすらしい」
- 「市丸さん、詳しいですね」
- 「檻の中で暇だから寝てんのかと思ってた」
- みんなで話しながら、葵くんのスケッチが終わるのを待つ。
そうして、いろいろな動物を見て、一日が過ぎていった。
- 「——そろそろ帰る時間だな」
- 日が傾いてきた頃、仁科先輩が腕時計を見て言った。
- 「うん……」
- 「まだ見たい動物いた?」
- 葵くんの表情が暗いのが気になって、聞いてみる。葵くんは首を横に振った。
- 「きょう、たのしかったから……かえるのさみしい」
- ぽつりと呟くように言う。私は思わず笑みを浮かべた。
- 「そうだね。……また今度、日向と東雲さんも一緒にみんなで来よう」
- 私の言葉に、葵くんも笑顔になる。
- 「……うん」

- 「おお、娘さんに日向! よろず妖屋の仕事はもう終わったのか?」
- 広間に入ると、寝転んでテレビを見ていたらしい東雲さんが、起き上がって聞いてきた。
- 「はい。今日はすぐに解決して」
- 「そうか。——しかし市丸の姿がないな」
- 訝しそうに東雲さんが首を傾げる。
- 「市丸さんは依頼主の方にお話ししてから帰るそうで」
- 「仁科たちはまだ戻ってねえのか?」
- 日向が尋ねると、東雲さんは困り顔でうなずいた。
- 「うむ。そろそろ腹が減ってきたのだがな」
- 東雲さんの言葉に、時計を見る。時刻は十二時ちょうど。今から作り始めたらいつもお昼ごはんを食べている時間になりそうだ。
- 「それじゃあ今から昼ごはんを作りましょうか」
- 「本当か!」
- 東雲さんがぱっと笑顔になる。そこへ旭が障子を開けて現れた。
- 「お嬢様、もうお帰りだったのですね」
- 「おお、旭! どうしたのだ?」
- 「今日は仁科様がいらっしゃらないので、代わりに昼食をご用意しようかと」
- 「本当に? 私も今から作ろうと思ってたんだけど……」
- 「お嬢様はよろず妖屋の仕事でお疲れでしょうし、俺が作ります。辰蔵様の分も作らなければいけませんし」
- そう言ってくれるけれど、旭も朝から働いているのに任せてしまうのは申し訳ない。
- 「うーん……あ、それじゃあ一緒に作ってくれる?」
- 私が言うと、旭は戸惑ったような顔をした。
- 「一緒に……ですか?」
- 「邪魔だったら、無理にとは言わないけど」
- 「いえ、そのようなことは。……それでは、お願いしてもよろしいですか?」
- 「うん。じゃあ行こうか」
- 旭と連れ立って台所に行こうとすると、日向が私の腕を掴んだ。
- 「待て。俺も手伝う」
- 「日向も行くのか? それなら僕も手伝おう」
- 東雲さんも立ち上がって言う。結局、そこにいた全員で台所に向かった。
- お昼ごはんはチャーハンを作ることになった。旭が冷蔵庫から青ねぎや豚肉、卵などを取り出す。
- 「ちゃーはんなら、作っているところをテレビで見たことがあるぞ! こう、フライパンを振って作るのだろう?」
- 東雲さんが手振りを交えながら尋ねる。
- 「いえ。家庭用のコンロは火力が弱いので、菜箸で混ぜながら中火で炒めた方がいいのです」
- 「へえ、そうだったんだ。うちでは振って作ってたよ」
- 「お嬢様の家のコンロは業務用で火力が強かったからでしょう」
- 旭の言葉に、日向が怪訝そうな顔をした。
- 「なんでお前がうちのコンロのこと知ってんだよ」
- 「……料理屋を営んでいらっしゃったので、そうなのではと思っただけです」
- 旭が答えても、日向は眉間にしわを寄せたままだ。
- 「お前って、なんか胡散臭えんだよな」
- 「日向、失礼だよ」
- 慌てて窘めるけれど、無視されてしまう。それを見て、東雲さんは突然日向と旭と肩を組んだ。
- 「まあまあ、二人とも仲良くしようではないか!」
- 「おい、暑いだろ! 放せ!」
- 「日向が旭と仲良くするならな」
- にっこりと笑って東雲さんが答える。
- 「私も仲良くしてほしいな……」
- 「ぐ……」
- 日向は苦虫を噛んだような顔をして、視線をそらした。
- 「——分かったよ。仲良くはしねえけど、けんかは売らねえ」
- 「そうか! よし、偉いぞ!」
- 「子ども扱いすんな!」
- 東雲さんに頭を撫でられて、日向が怒って手を払う。
- できれば東雲さんとも仲良くしてほしいのだけれど……当の本人は気にした様子もなく笑っている。
- 「あの……ありがとうございます」
- 傍に寄って小声で言うと、東雲さんは優しく笑ってみせた。
- 「うむ。みんな仲良くするのが一番だからな」